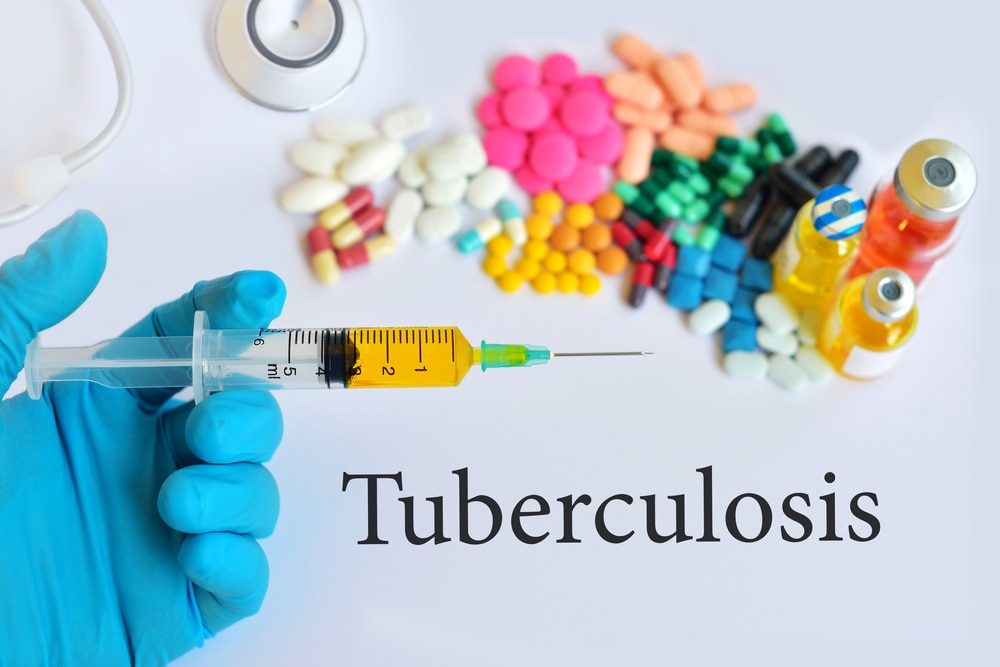
医薬品・医療機器 翻訳サービス:翻訳に必要な医学的知識 No.7 | 結核の治療 ③
川村インターナショナルの医薬品・医療機器・医学翻訳 サービス
川村インターナショナルは、医薬品・医療機器等の開発から市販後の様々なコンテンツ、研究機関、病院、介護施設などの多様なニーズの医薬品・医療機器・医学翻訳に、医療翻訳案件専門チームが対応し、AI活用による翻訳サービスにも対応しています。専門性の高い医療翻訳サービスも安心してお任せ下さい。
結核の治療③
化学療法(Chemotherapy)
抗結核剤の臨床投与が可能となったことにより、結核治療は劇的に進歩し、大気安静療法、人工気胸療法、および胸郭形成など、それまでの結核治療法はいずれも過去のものとなり、結核療養所の象徴的存在であったアメリカのTrudeau Sanatoriumは1954年に、ヨーロッパの結核療養所も1965年頃にはほぼ総て閉鎖となった。
結核罹患率が高かった日本では、結核療養所の閉鎖は欧米よりも遅れ、「国立療養所」の名称がなくなったのは平成16年以降である。
主な抗結核剤と、その開発年を以下に示す。
1945年(昭和20年) ストレプトマイシン
1946年(昭和21年) PAS(Para-amino Salicylic Acid パラアミノサルチル酸)
1952年(昭和27年) イソニアジッド(INH イソニコチン酸ヒドラジッド)
1963年(昭和38年) エタンブトール(EB: Ethambutol)
1967年(昭和42年) リファンピシン(RFP: Rifampin)
1.結核化学療法の基本
どの抗結核剤に対しても、結核菌は約107個に1個の割合で自然耐性菌が存在する。空洞が生じると酸素供給がよくなるため結核菌の増殖は活発となり、病巣の菌数は109にも達する。
菌数が増えれば、耐性菌が自然発生する確率は高くなり、単剤で治療すると、感受性菌は死滅しても、耐性菌は生き残り、数カ月後には総てが耐性菌に入れ替わる。したがって、結核の化学療法では、必ず多剤投与(Multidrug Therapy)とし、単剤投与(Single Drug Therapy)は絶対に行ってはならない。
作用機序が異なる2剤で治療した場合、両剤に対する自然耐性菌の出現確率は107x107分の1、すなわち耐性菌は1014個に1個の割合で、たとえ空洞に大量の菌があったとしても、自然耐性菌が出現する確率は極めて低くなる。
現在行われている、標準的化学療法では、3~4剤の多剤療法を基本としているので、患者さんが指示通り服薬している限り(=Good Compliance)、多剤耐性結核菌(MDR: Multi-Drug Resistant ) の出現確率は、十分低くなる。
2.初期の三者療法:INH, PAS, SM
昭和42年にRFP(リファンピシン)が出現するまでの標準的結核化学療法は、パス(PAS)、ヒドラジッド(INH)、ストレプトマイシン(SM)の三者療法だった。治療期間は最低でも1年以上で、治療終了時期は、明確には規定されていなかったため、何年間も服薬を続け、療養所を現住所とし、家財道具まで持ち込む患者さんもいた。
ストレプトマイシン(SM)は連日筋注投与としたことが多かったため、当時の患者さんの中には、SMの副作用により、その後、難聴やめまいで悩んだひとも多くいた。
3.標準三者療法:INH, RFP, EB
PASは1日10g散剤投与で、量が多い上に飲みにくかったため、昭和38年以降はエタンブトール(EB)に、また、昭和42年以降は、筋注投与のストレプトマイシンは経口投与のRFPに、それぞれ代わった。標準投与期間は9カ月としたが、糖尿病などの基礎疾患がある場合は、投与期間は1年以上に延長した。
4.短期化学療法(Short Course Chemotherapy)
現在の標準的治療法で、INH,RFP,EB,PZA を2カ月、INH,RFP,EBを4カ月、計6ケ月で完了する。
1980年頃から世界的に、この6カ月短期化学療法が主流となり、最初の2カ月を4剤(INH, RFP, EB, PZA(ピラジナミド))、次の4カ月はPZAを除いた3剤とした。しかし、平成22年頃からは、わが国でも、最初の2カ月は4剤、後半の4カ月はINH, RFPの2剤投与でもよいことになっている。
5.予防的治療(Preventive Chemotherapy)
喀痰塗抹陽性(Smear Positive)の結核患者と、じかに接触したひとを潜在性結核(Latent Tuberculosis)と規定し、予防的治療(Preventive Chemotherapy)の対象とする。予防的治療では、通常、INH1剤を6ヶ月投与する。
結核の化学療法では、1剤投与は絶対にしてはならないと先に述べたが、予防的治療では、なぜ、INH単剤でよいとされているか?答えのヒントは、結核を発病した患者の保菌数と、接触感染後間もない(=結核発病前)、潜在性結核患者の保菌数の違いにある。
当然、前者の方が後者よりも保菌数は圧倒的に多い。保菌数が少ない、潜在性結核患者に自然耐性菌が存在する確率は、セロではないが、極めて低いと考え、1剤投与で十分としている。
6.化学療法で結核は完治するか?
化学療法により、発熱、せき、たん、体重減少などの結核症状は急速に改善し、2~3カ月で患者さんは、もう治ったと思うほどに回復する。6カ月の短期化学療法で、結核は臨床的には完治すると思ってよい(=臨床的治癒)。
しかし、体内にあった結核菌が総て駆除すること(=細菌学的治癒)は、実際には不可能で、リンパ節や陳旧性結核病巣内には休眠状態で生き残った結核菌が存在する。化学療法がどんなに進歩しても、臨床的治癒は可能であるが、細菌学的治癒は不可能であることは十分認識する必要がある。
現在、日本の結核患者の約70%を占める高齢者結核例の多くは、若い頃に結核を発病、治癒した症例で、50年以上後の再発例である。
川村インターナショナルの翻訳サービス
川村インターナショナルは、プロフェッショナルな人材のコラボレーションによる人手翻訳に強みを持っています。IT、医療、法律、金融などの専門分野に対応し、英訳をはじめ40言語以上の多言語の組み合わせをサポートしています。ネイティブチェック、専門家レビューなどのオプションもございます。
統計的な品質管理手法に基づく品質保証で短期・長期の案件で安定した品質を実現します。翻訳サービスの国際規格 ISO17100と情報セキュリティに関する国際標準規格 ISO27001(ISMS認証)の認証も取得しています。
関連記事








