- TransReed限定版
- Seven Eight Nine,7が8を9った?駄洒落と翻訳
「布団が吹っ飛んだ!」
「牛が笑ってうっしっし」
「マイケル・ジョーダンの冗談はまぁいける冗談」
なんだか背筋に冷たいものを感じてしまいましたが、これらのギャグを英語に訳そうとするとどうなるでしょうか?
今回の記事では、翻訳の中でも「駄洒落」の翻訳がなぜ難しいかについて考えてみます。

直訳できない駄洒落
冒頭の駄洒落を翻訳するとなると、「うまい!」と唸らせるような訳を作りたいのに、思わず考え込んでしまいます。
現在では、海外でも"futon"が寝具の一種として認識されますが、”The futon has futtonda!” と言っても一体何なのかもわかりませんし、おもしろくもなんともありません。
「うっしっし」も、日本語特有の笑い声の擬音語なので、英語ではhahahaやheeheeなどと訳さなければ通じませんが、「牛」と同じ音ではないので掛詞、親父ギャグのもつユーモアにはなりません。
ちなみに、日本語学習者にとって最も学習の難しい項目のひとつが「擬音語/擬態語」であると聞いたことがあります。日本語がかなりペラペラな韓国人の友人が「テカテカって何ですか?」と聞いてきたときは、擬音語・擬態語の難しさを知ったものでした。
「マイケル・ジョーダン」も外国人の方の名前の音を日本語の音と掛けているので、訳するのは至難の業です。訳せて通じたとしてもマイケルに怒られそうなだけで、笑いを誘えるかは怪しいです。
このように、駄洒落では、その言語特有の「音」を掛けているものが多く、直訳しても駄洒落の意味を成しません。このような場合では、翻訳対象言語で一般的に使われる駄洒落にまるまる置き換えてしまうことが多いようです。

英語の駄洒落はどんなもの?
では、逆に英語の親父ギャグを日本語にうまく訳せるのでしょうか。次の英語のギャグを訳すことはできますか?
|
“I want to take a moment to recognize the brave turkeys who weren't so lucky. Who didn't get to ride the gravy train to freedom. Who met their fate with courage and sacrifice and proved that they weren't chicken.”
“We should also make sure everyone has something to eat on Thanksgiving. Of course, except the turkeys, because they're already stuffed.” |
いかがでしょうか?
ちなみに、英語で「親父ギャグ」はdad jokes、daddy’s jokesと呼ばれています。ある意味直訳、親父ギャグの文化は東西共通なのですね。
これらのギャグは、元アメリカ大統領のオバマ大統領により、感謝祭(Thanksgiving)の直前に行われるターキーパードンで言われたものです。アメリカでは、感謝祭のメインディッシュに七面鳥(ターキー)を食べる文化があり、感謝祭シーズンには数千万羽もの七面鳥が食されます。ターキーパードンでは、選ばれた七面鳥2羽がアメリカの大統領により恩赦され、その後飼育されることになっています。そこでのスピーチで使われたギャグです。
言葉あそびが巧みな英語の駄洒落
一つ目のギャグは”gravy”と文末の”chicken”がポイントとなります。
gravyとは「肉汁」のことです。つまり、「ウマイ汁」なので、ride the gravy trainという成句は、「おいしい仕事、楽してお金儲けのできる仕事」のことです。そして、アメリカの感謝祭のご馳走のメインである七面鳥と他のおかずは、gravy sauce(グレービーソース)という肉汁と野菜の出汁から作られたソースで食べます。なので、”Who didn't get to ride the gravy train to freedom.”とは、自由への切符を手に入れることなく、食べられてしまったターキー達のことを思い、追悼の意を述べています。
さらに、最後の”Who met their fate with courage and sacrifice and proved that they weren't chicken.”ですが、これをそのまま訳すと「彼らは果敢に運命と向かい合い、犠牲になることで鶏でないことを証明した。」となります。ここでの運命とは、食べられてしまうことです。
七面鳥はもちろん鶏ではないので文字通り、鶏でないことは証明されます。その一方で、chickenは「臆病者、弱虫」という意味も持つので、生き残った2羽の犠牲となり食べられてしまうことで「臆病者、弱虫」ではないことを証明したという意味が隠されています。
こういった理由で、一つ目のギャグでは”gravy”と”chicken”が掛詞となります。
文化や背景が関わる駄洒落
二つ目のギャグは文末の”stuffed”がキーワードです。
文頭の「感謝祭ではみんなに十分な食べ物があるようにしないといけない。」に続き、”Of course, except the turkeys, because they're already stuffed.”「もちろん、七面鳥以外だけどね。彼らはもう満腹だから。」とあります。”stuffed”は、「詰まった」という意味をもち、ここでは「満腹」ということです。
では、なぜ七面鳥達はお腹が一杯なのでしょうか?
もう一つの意味は七面鳥の調理方法に答えがあります。感謝祭の七面鳥は、オーブンで焼かれる前にお腹に刻んだ野菜を詰められるのです。つまり、お腹が「いっぱい」なのです。
なので、このギャグの掛詞は”stuffed”になります。
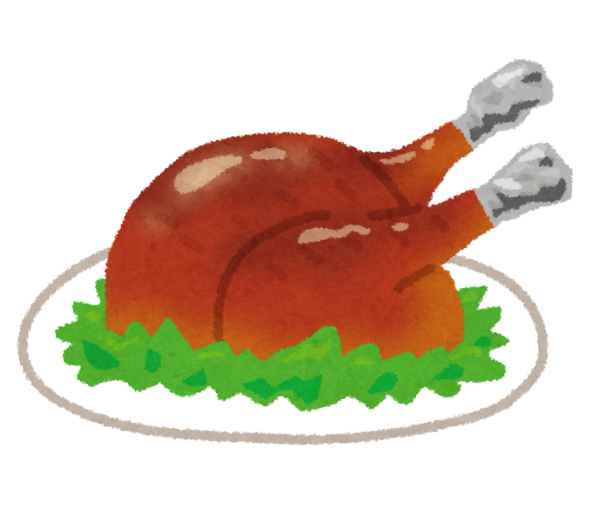
では、これを踏まえて、本題へ戻ります。
この2つのギャグのユーモアを残したまま、日本語へ訳せるでしょうか?
これも、思わず悩んでしまいます。
なぜ七面鳥がアメリカの大統領に栄誉を称えられているのか、なぜみんなはお腹一杯になるほどのご馳走が用意されるのに七面鳥は何も食べさせてもらえないのか、理由が伝わらなければ、面白さは伝わりません。
駄洒落は翻訳者泣かせ!
では、なぜこれほどにも親父ギャグは訳するのが難しいのでしょうか。
もう大体お分かりかもしれませんが、親父ギャグには各国の文化や習慣に基づいている内容や、その言語特有の音や発音により笑いを誘うものが多いからです。
これらを翻訳するには、まずギャグに気づかなければなりません。そして、そのギャグは翻訳をしても意味が通じるかどうか、おもしろいかをどうかを判断し、翻訳をします。上の例のように翻訳が難しい場合は、その場面に合ったジョークを一から作り、対象言語へ翻訳をします。ユーモアのセンスが問われてしまいます。
一からジョークを作り直している場面はよく映画の字幕で見受けられますよね。役者の言っているジョークが字幕の日本語では違うジョークとなって表示されているのをよく見ます。
例えば、『マネー・ショート』(2015年・米)という映画のあるシーンで「It's like two plus two equals... fish!」というセリフが出てきます。
ジョークではありませんが、これは言わば「1+1は田んぼの田」と同じような理屈で、2をひとつ反転させて、普通の2と反転した2をくっつけると魚の形になることを表現しており、アメリカではなぞなぞや、ひっかけ問題として使われることがあるようです。このシーンでは、支離滅裂なことの例えとして使われていました。
しかし、字幕や吹き替えで急に「2+2は魚!」と言われても、なんのことかさっぱりわかりません。結局、このシーンの字幕では「支離滅裂じゃないか!」というような、本来意味したかったことが率直に日本語になって表現されていました。
映画やドラマ、そして小説など書籍の翻訳でも、翻訳者泣かせなジョークは散見されます。意識して探してみると、面白いと思います。

おわりに
各言語の言葉遊びや、ギャグはそれぞれのバックグラウンドがあってこそ面白いものです。
翻訳を仕事にしている方たちにとっては永遠の課題であり、その面白さを伝えきれないもどかしさが付きまとうと思います。でも訳せない場面に直面したときこそ、言語の深みやおもしろさを噛みしめたいものです。
下のフィードバックフォームよりお気軽にお知らせ下さい!
例えば・・・
CATツールを自社に導入したいが、どれを選べばいいか分からないのでオススメを教えてほしい。
機械翻訳と人手翻訳、どちらを選ぶべきかわからない。
翻訳会社に提案された「用語集作成」ってどんなメリットがあるの?
ご意見ご要望をお待ちしております!



