英語の会議に臨む前に
知っておきたいこと!
(資料作り編)
英語の会議に臨む前に
知っておきたいこと!
(資料作り編)
英語の会議は緊張しますよね。いつにも増して、資料作りにも力が入るかと思います。
ちょっとした工夫をするだけで英訳したときに違いが表れます!初めから英語で作る場合にも役立つと思いますので、普段あまり考えない日本語と英語の違いについて考えてみましょう。
そして、より効果的な資料を作ることで発言力を高めましょう!

日本語って便利だなーと思うのが熟語です。資料に表やグラフを入れる場合でも、少ないスペースを使って短い言葉で説明できるのがとても楽ですよね。
ただ、いざ英訳するときによくよく考えてみると読む人によって違う解釈ができる熟語が沢山あることに気が付きます。
今回の記事では翻訳会社ならではの視点で、「これはつまり…どういう意味なんだろう」と私自身が感じた熟語や、ネイティブから訳しづらいと不評な熟語(笑)、熟語以外でも訳すときに気になる日本語の例をいくつか紹介したいと思います。
「2020年までに○○を実現」、なんて書くだけで確かに締まりますが、英語で何と訳せばよいか想像したことがありますか?
直訳すると realize になりますが、使うシチュエーションとしては「自己実現」のようなときで、あまり自然とは言えません。どんなニュアンスをもたせたいかで「実現」の代わりに、「達成」や「完成」など、原文を変えてみると良いかと思います。
これも日本語ではよく使われるものの、英語ではそこまで使わない言葉の一つです。
売上数値の説明などで「予測」「実績」とは英語でも言いますが、営業の売り文句で「過去の実績を見ればお分かりいただけます!」というような表現は英語ではあまりしません。つまりは、英語ではもっと具体的に説明することが多く、「実績」という一言で「豊富な経験値」と読み替えてくれるわけではないのです。
英語のプレゼンでは、「実績」一言で済ますのではなく、どのようなことを達成してきたか、具体的に記載してみることがおすすめです。
どんな場面でも使える便利な日本語ですね。だからこそ訳者は困るのかもしれません。
これも具体的な言葉に置き換えたほうが伝わりやすいでしょう。「対応を検討中」なら「取り扱い」や「対策」に、「第4四半期中に対応」なら「修正」「実行」などに置き換えられるかもしれません。
もしかしたら日本を一番感じる熟語かもしれません。
「担当から連絡させます」など、具体名を言わなくても伝わる究極に便利な言葉ですね… お気付きかと思いますが、アメリカでは存在しません(笑)。英語ではたとえばチーム編成などの話をしていたら in charge of と言うかもしれないですが、主語としては使いません。では、何に変えれば良いか。ずばり実際の役職や肩書です。たとえば、sales representativeやcoordinatorなど具体的なものに置き換えましょう。
これが一番訳しづらいとネイティブからよく言われます。
確かに直訳してtargetと言っても意味が分からないし、幅広く使える言葉ですよね。たとえば「見積り対象外」のように使う場合、「見積りには含まれません」と言い換えたら英訳も分かりやすくなると思います。
日本人が作る資料には「など」が多いですよね。(私もこの文章中に何回使っていることでしょう!)
アメリカでも契約書みたいにリスクがあるものには including but not limited to という言い回しでぼかしたりしますが、基本的に普段の資料ではストレートな表現を使います。箇条書きで「など」をあまり使いすぎるとしつこいですし、かえって分かりづらくなる可能性もありますので、多用せずにシンプルにしましょう。
どうしても「など」を使いたい場合は、「などの○○」の対象を明確に示すと、英語でもスッキリ分かりやすくなります。例えば、「バナナ、ミカンなどはおやつに含まれません」ではなく「バナナ、ミカンなどのフルーツはおやつには含まれません」としてみるのはいかがでしょうか。
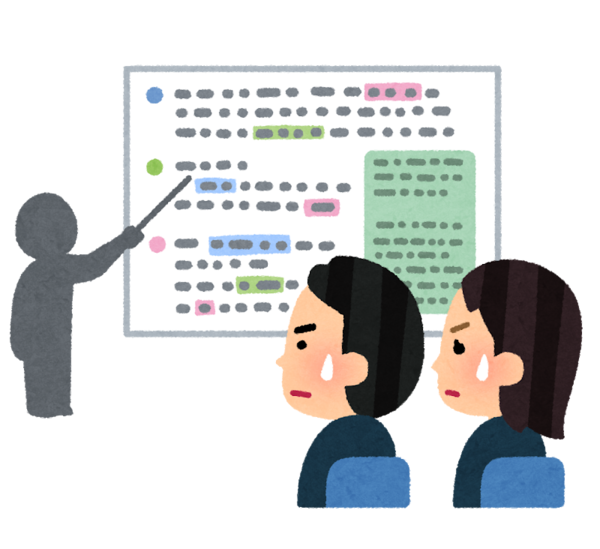
記号も言葉と同じように各国で使い方は変わってきます。置き換わる記号が存在しないものすらあります。では、例を挙げながら見ていきましょう。
日本語では強調したいときに「」を使ったり、見出しのような形で【】を使ったりすることが多いですよね。
「」を英語で書くなら“”になりますが、あまり多用するとややうるさい印象になってしまいます。もしどうしても強調したい箇所があれば、下線や太字にしてみましょう。赤字を使う方もいますが、きつい印象を与える可能性もあるので避けたほうが無難かと思います。
【】にいたっては、置き換わる記号が英語に特にないので、むしろ最初から使わないほうが良いかもしれません。見た目が似ていることから [ ] にする場合もありますが、一般的に強調や見出しの用途で使わない記号なので原文と同じニュアンスでは伝わらないと思ったほうが良いでしょう。
表を使って情報を伝えれば、すっきりとまとまりますし、万国共通で見やすいですよね。ただ、日本の表でよく使われる ○=良い、×=ダメ、△=どちらでもない、という意味合いの記号は英語では全く通じません。単なるマークにしか見えないので、そういう意味をもたせたい場合は ✔やYes/Noなどを使いましょう!
余談ですが、アメリカのレストランでお会計をお願いする際に「締めてください」の意味として手で×を作っても全く通じませんので気を付けましょう。

ここまで読んできて改めて感じたかもしれませんが、単に言葉をそのまま訳しても意味は伝わりません。
言葉はまさに文化を反映します。他国の文化を完全に把握するのは難しいですが、せっかくの資料をもっと効果的に使うためにも、まずは日本の当たり前は世界の当たり前ではないと認識しましょう。そうすることによって、使う表現自体も変わってくるかと思います。
たとえば、何かの基準策定について書くとします。日本語で「国と同等の基準で地方自治体も策定すべき」と書いてあったら、どういう印象を持ちますでしょうか?おそらく日本人であれば「国の基準>地方の基準」と思いますよね。ただ、これをそのまま英語にしてアメリカ人が見たらどうでしょう。文字どおり「国と地方の基準を同等にする」としか読み取らず、どちらが上というイメージは伝わらないかと思います。
その背景として、国主導の日本に対し、アメリカではむしろ州のほうが強かったりもします。つまり、この日本語は「地方自治体よりも国のほうが厳しい基準を持っているはずだ」という考えのもとに作られているわけですが、この前提を持たないアメリカでは、そのまま英語に訳しただけでは通じません。本来の意味を伝えたいのであれば、「国と同等の厳しい基準で地方自治体も策定すべき」と補足が必要になります。

さて、そろそろ結論に入ります。いろいろと書いてきましたが、一番大事なことはこの見出しに書いてあるとおり「伝えたいことをシンプルに伝える」ということです!
当たり前なことですが、改めて意識してみましょう。口癖と同じように書き言葉にも癖があります。こう書けば体裁が整う、この表現なら重みがある、そんなふうに考えて資料を作る時もありますよね。
日本語の会議ならそのイメージどおりに伝わるかもしれませんが、英語に翻訳した場合は必ずしも同じニュアンスになるわけではないので少し注意が必要です。日本語の言い回しはさておき、「つまりここで伝えたいことは何だろう…」と一呼吸を置いて考えてみてください。日本語の表現を少しシンプルにするだけで、英訳した後も伝えたいメッセージが生きてくるはずです。
あとは、あまり情報を詰め込みすぎないことも大切ですね。アメリカ人のプレゼン資料を見たら、おそらく余白が多くてびっくりすると思います(笑)。普段そういう資料に慣れている方々の目をチカチカさせない程度の情報量にしましょう。