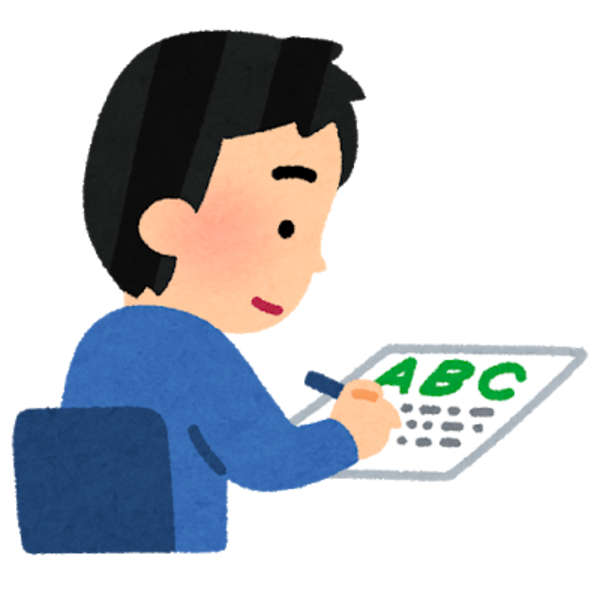ポストエディットのむかしとこれから
筆者(スウェーデン人)は川村インターナショナルでポストエディット業務に携わっています。ここでは、筆者のポストエディットとの出会いについて簡単に触れてから、業務を通して学んだことをご紹介します。
筆者が初めてポストエディットに関わったのは数年前のことです。もっとも、その時はポストエディットの存在を知りもしませんでした。2015年の末、大学の授業で日本語の心理学論文を英訳する課題があり、友人が機械翻訳を使って翻訳したものを苦労しながら直しました。自分で翻訳する方が効率的だなんて考えたりしました(その課題が翻訳に興味を持ち始める一つのきっかけになったのはまた別のはなしです)。
この数年前から、機械翻訳とポストエディットは著しく変わってきているようです。
|
目次
|

略語説明
翻訳業界では、機械翻訳に関連した略語が多く使用されています。ここでいくつかご紹介します。
- MT:「Machine Translation」いわゆる機械翻訳。
- NMT:「Neural Machine Translation」ニューラルネットワーク(AI)を活用したニューラル機械翻訳。Google翻訳はNMTを使用しています。
- SMT:「Statistical Machine Translation」統計的機械翻訳。
- HT:「Human Translation」翻訳者が行う従来の翻訳。日本語では、「機械翻訳」に対して「人手翻訳」などと呼ばれます。
- PE:「Post-edit」ポストエディット。機械翻訳を後編集して訳文を完成させることです 。
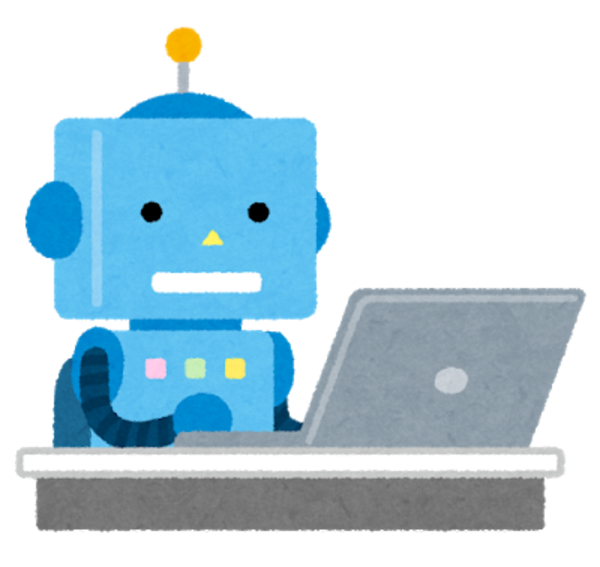
ポストエディットとは?
ポストエディットの種類:フルポストエディットとライトポストエディット
ポストエディットと人手翻訳の違い
機械翻訳の発展
ひと対機械
いつまでもAIに学ばせることができないものは何でしょうか。それは感情や文化といった人間らしさです。
人手翻訳と機械翻訳、ポストエディットの違いを考えるとき、この点もまた一つのポイントです。AIには正しい文章を吸収することはできても、感情、文化や文脈は吸収できません。そのため、ポストエディット前の機械翻訳結果には、どうしても直訳になってしまう部分が出てきます。
それに対して人手翻訳では、ヒューマンエラーと言って、原文にない内容まで書いてしまったり、その逆に原文にある内容を書かなかったり、数字を間違えたりと、不注意によるミスが生じます。
原文をプリエディット(前編集)して機械翻訳をかけやすくすることも可能ですが、やはり原文の内容によって向き不向きはあります。機械翻訳と人手翻訳のどちらかをなくすことはできないので、互いが互いを補い合える状態が理想なのではないでしょうか。
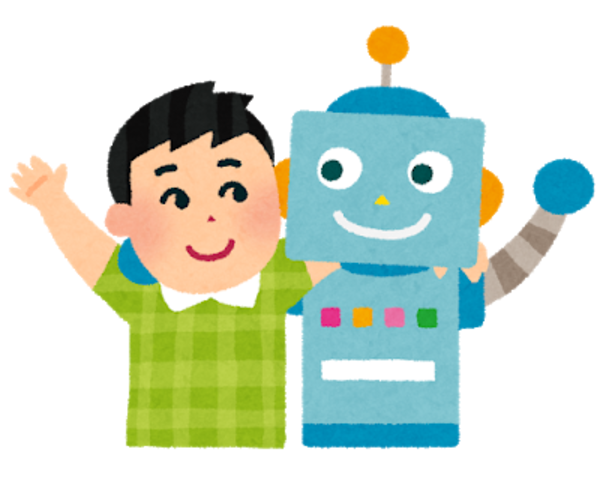
今後のポストエディット
フィードバックフォーム
当サイトで検証してほしいこと、記事にしてほしい題材などありましたら、
下のフィードバックフォームよりお気軽にお知らせ下さい!
例えば・・・
CATツールを自社に導入したいが、どれを選べばいいか分からないのでオススメを教えてほしい。
機械翻訳と人手翻訳、どちらを選ぶべきかわからない。
翻訳会社に提案された「用語集作成」ってどんなメリットがあるの?
ご意見ご要望をお待ちしております!
下のフィードバックフォームよりお気軽にお知らせ下さい!
例えば・・・
CATツールを自社に導入したいが、どれを選べばいいか分からないのでオススメを教えてほしい。
機械翻訳と人手翻訳、どちらを選ぶべきかわからない。
翻訳会社に提案された「用語集作成」ってどんなメリットがあるの?
ご意見ご要望をお待ちしております!
新着記事一覧